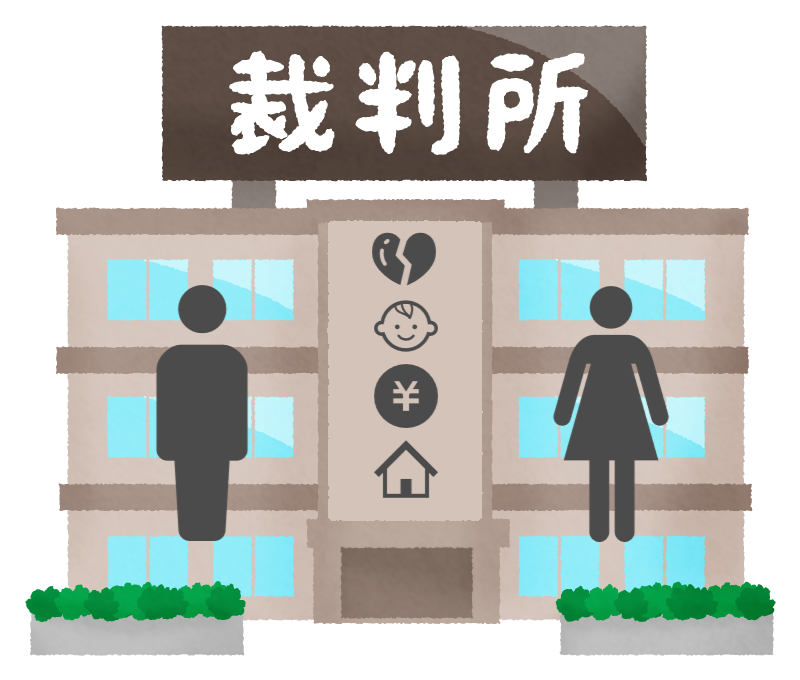不受理申出とは、身分関係(親子や夫婦など親族内の地位)を変動させる一定の届出が、本人以外から届け出られても市区町村が受理しないよう事前に申し出ることができる制度です(戸籍法第27条の2第3項)。
不受理申出の対象となる5つの届出
- 婚姻届
- 協議離婚届
- 養子縁組届
- 協議離縁届
- 認知届
不受理申出がよく利用されるケースとしては、勝手に出されてしまう離婚届の防止のほか、近年では知らないうちに行われる養子縁組届の防止です。
何のために養子縁組届の不受理申出? と思うかもしれませんが、養子縁組で戸籍と氏が変わる効果は、悪用されている現状があって(ネームロンダリングとも呼ばれます)、本人確認等で予防措置はされているものの、完全には防止できていません。
そこで、誰かと婚姻していた、勝手に離婚されていた、誰かと養子縁組していたなど、思いもよらない身分関係が生じないように、不受理申出で届出が受理されるのを防ぐのです。
不受理申出制度が設けられた経緯と利用状況
不受理申出の対象となる5つの届出は、全て届出によって身分行為(身分の取得や変動)の効力が生じる「創設的届出」と呼ばれるものです。
創設的届出は、当事者の意思がなければ当然に無効ですが、一旦受理されると戸籍訂正は容易ではなく、家庭裁判所に無効確認を訴えるしかありません。
ところが、市区町村の戸籍担当者は、届書(届出に使われる用紙)が提出されたとき、届書の内容に記載漏れや法令違反が明らかでなければ受理します。
届出が疑わしいときは、管轄の法務局に受理照会をする扱いですが、短期間に養子縁組が繰り返されているなど、受理照会は相当に疑わしいケースだけで、当事者の一方が窓口に来ない程度では行われません。
そうすると、戸籍という身分を決める重要な届出にもかかわらず、当事者の意思がない届出でも、問題なく受理される可能性が出てくるわけです。
つまり、当事者の意思がない届出は、当事者の意思に基づいてされるほとんどの届出と表面上区別できませんが、一部の不正な届出のために、厳密な当事者の意思確認をしていくのも現実的ではないでしょう。
そこで、届出を受理されたくない当事者から申し出ることで、届出意思が不存在の届出を未然に防止できる仕組みとして、不受理申出制度が設けられました。
不受理申出がされている件数
戸籍統計によると、毎年度24,000~28,000件程度の不受理申出があります。
| 令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度 | 平成30年度 | 平成29年度 |
|---|---|---|---|---|
| 24,008 | 25,408 | 27,329 | 27,060 | 27,671 |
※他市区町村から送付されたものを含まない
不受理申出制度の存在が、少しずつ知られてきた表れともいえますが、対象の届出は5つあることを考えると、まだまだ周知には至っていないのかもしれません。
もっとも、婚姻していないのに離婚届の不受理申出をする必要はなく、婚姻中なのに婚姻届の不受理申出をする必要はないのですから、現在置かれている状況によって、不受理を申し出るべき届出は変わります。
不受理申出書のダウンロードについて
不受理申出書は、全国どこの市区町村で入手しても大丈夫ですし、面倒ならダウンロードも可能です。ただし、白紙の不受理申出書がダウンロードできる自治体は多くありません。
不受理申出は、本人が市区町村に出頭して申し出るのが原則で(戸籍法施行規則第53条の4第1項ならびに第2項)、そもそもダウンロード提供の需要が小さいのです。
北海道札幌市:不受理申出
※別ウィンドウまたは別タブで開きます。
特に書くのが難しい届出でもないので、どうしても窓口に出頭できない場合や、どういう書式か事前に知っておきたい場合に利用してください。
不受理申出書の書き方
不受理申出書の記入欄は少なく、本人出頭を原則としていることからも、不明な点は窓口で聞けばそれで済みます。しかし、記入欄がなぜそうなっているのか、理解した上で書かないと難しいかもしれません。
以降、前述のダウンロード可能な不受理申出書を前提に説明します。
欄外:申出日
不受理を申し出る年月日を書きますが、原則は本人出頭でも、やむを得ない理由があって出頭できない場合は、特定の要件(後述)を満たすことで郵送もできます。
よって、不受理申出書の申出日は受理日と一致しない可能性があります。だからといって、郵送の場合に不受理申出書に記載された申出日まで遡ることはありません。
欄外:宛先
必ず申出人の「本籍地」の市区町村長です。本籍地以外の市区町村で不受理を申し出る場合も、宛先は本籍地の市区町村長となります。
例外は、申出人が外国籍で日本人を相手方とする不受理申出では、相手方日本人の本籍地を管轄する市区町村長が宛先になります。
不受理申出の対象となる届出
不受理申出書は届出別の用紙になっており、届出の種別が記載されていることを確認します。
なお、過去にした不受理申出があれば、その旨をチェックしますが、これは、同じ効力の申出が有効なときは、重複して(不受理申出を)受理せずに不受理にするためです。
申出人の表示等
この欄は、不受理を申し出る届出によって異なります。
| 不受理申出する届出 | 申出人の記載 | 相手方の記載 |
|---|---|---|
| 婚姻届 | 申出人 | 夫又は妻になる人 |
| 協議離婚届 | 申出人 | 夫又は妻 |
| 養子縁組届 | 養子になる人 | 養親になる人 |
| 協議離縁届 | 養子 | 養親 |
| 認知届 | 申出人 | 認知される子 |
どの用紙でも、申出人と相手方について次の内容を記入しますが、相手方についての記入は必須ではありません(相手方を特定できない場合があるので)。
- 氏名
- 生年月日
- 住民票上の住所
- 本籍
- 筆頭者氏名
これらの記入自体については特に問題ないはずです。住所については番地と番の選択があり、該当する方を○で囲むか該当しない方を線で消せば良いでしょう。
申出人が外国籍の場合は氏名をカナで、本籍欄は国籍を記入、相手方の氏名、本籍、筆頭者氏名をその他欄に記入します。
その他
前述の通り、外国籍の申出人の場合に相手方の記入に使われます。
※他の用途は不明なため、わかりしだい追記します。
申出人署名
問題ないでしょう。当然ながら申出人の自署でなくてはなりません。
申出人連絡先
不受理について連絡がある場合に備えて、確実な連絡先を記入します。普通は、現住所と平日の昼間に通じる電話番号を記入しておくのが最も確実です。
※他の記載パターンについては、わかりしだい追記します。
不受理申出書の提出方法と提出先
市区町村に本人が出頭し、不受理申出書によって申し出るのが原則で、本人確認と不受理申出書に不備がなければ受理されます。不受理申出の性質上、届出の当事者になり得ない人が不受理申出をすることはできません。
不受理申出の申出人
- 婚姻届:夫又は妻になる人
- 協議離婚届:夫又は妻
- 養子縁組届:養子になる人(15歳未満は法定代理人)又は養親になる人
- 協議離縁届:養子(15歳未満は離縁後に法定代理人となるべき人)又は養親
- 認知届:認知する人
※法定代理人とは親権者や未成年後見人です。
15歳未満を対象とした養子縁組届では、養子になる人が共同親権に服しているとき、共同親権者のどちらも申出人になることができます。
また、15歳未満を対象とした協議離縁届では、離縁後の法定代理人が該当するので、不受理申出がされる協議離縁前の段階では、法定代理人と「なるべき人」です。
認知届では、認知する人(つまり父)からしか申出できず、認知される人(認知される子や法定代理人)からは申出できないので注意しましょう。
不受理申出に持参するもの
- 不受理申出書
- 本人確認書類
郵送や使者による不受理申出
申出方法の例外として、申出人が出頭できない場合、郵送による申出と本人以外の使者による申出も認められていますが、他の届出と違って要件がかなり厳しいです。
郵送や使者による不受理申出では、公正証書または公証人の認証を受けた私署証書を提出することで(もしくは準ずる方法によって)、不受理申出が申出人本人によるものだと明らかにしなくてはなりません。
そして、公正証書または認証を受けた私署証書には、必ず次の事項を含めます。
公正証書または認証を受けた私署証書に含める事項
- 不受理の申出をする旨
- 申出年月日
- 申出人の氏名、生年月日、住所、本籍、筆頭者氏名
- 15歳未満の養子縁組で法定代理人による申出の場合は、養子になる人の氏名、生年月日、住所、本籍、筆頭者氏名
- 15歳未満の協議離縁で離縁後の法定代理人になるべき人による申出の場合は、養子の氏名、生年月日、住所、本籍、筆頭者氏名
公正証書による方法
申出人本人が、公証役場の公証人に、前述の必要事項を記載した公正証書を作ってもらいます。
認証を受けた私署証書による方法
申出人本人が、前述の必要事項を記載した書面に署名押印し、それを公証役場に持ち込んで公証人に認証してもらいます。
代理人への依頼は不可
一般的に、公正証書の作成や私署証書の認証は、代理人による嘱託が可能ですが、不受理申出書に添付する場合は、本人からの嘱託が絶対条件です。
ここで、公証役場に行けるなら、本人が役所に行って申出すれば良いと思うかもしれませんね。
しかし、入院中などで動けなくても公証人は出張できるので、公正証書や認証を受けた私署証書が作成でき、郵送や使者による申出が可能になります。
本籍地以外での不受理申出
不受理申出は、本籍地以外にも住所地や所在地の市区町村に申し出ることが可能です。
本人確認後に受理されるのは同じですが、本籍地ではないので謄本を作成して保管し、不受理申出書の原本は本籍地の市区町村へ送られます。
ただし、15歳未満が対象である場合、養子縁組届においては法定代理人が、協議離縁届においては法定代理人になるべき人が申出人となるので、申出人の本籍地と養子になる人または養子の本籍地は異なる場合があります。
その場合、申出人の本籍地の市区町村で原本が、養子になる人または養子の本籍地の市区町村(申出されたどちらの本籍地にも該当しない市区町村を含む)で謄本が保管されます。
時間外の不受理申出
不受理申出は、本人からの申出が確認された場合しか受理できない性質から、時間外(閉庁日や夜間)の申出書は受け付けない市区町村がほとんどです。
一部の市区町村では、時間外でも特定の時間帯(開庁前・閉庁前の一定時間、閉庁日の昼間など)は受け付けていることがあります。
こうした対応の違いは、時間外に宿日直の職員が本人確認できるか、時間外は守衛だけで本人確認できないかの違いで、もし申出書を受け付けてもらえても、審査は翌開庁日となります。
また、極めて僅かだと予想されますが、ごく一部の市区町村では時間外での不受理申出があると、本人確認のために職員を呼び出して対応するようです。
※いつまで同様の対応がされるかは定かではありません。
不受理申出の受理後と不受理通知
本来、不受理申出の有無と関係なく、市区町村の戸籍担当者は、対象となる5つの届出があったときに、届出の当事者から不受理申出がされていないか確認します。
不受理申出があった申出人の本籍地の市区町村では、戸籍簿に着色用紙を綴じ込んだり、戸籍システムの画面上に不受理申出がある旨を表示させたりして、不受理申出があったことを確認できるようにする措置を施します。
ただし、当事者全員の本人確認がされた届出は、仮に不受理申出があっても受理できる申出人からの届出になるため、不受理申出の有無は確認されません。
では、本籍地以外に対象の届出がされた場合はどうなるのでしょうか?
本籍地以外に届出があると、本籍地の市区町村に対し電話等で不受理申出されているか確認されます。その上で、本籍地に不受理申出がされておらず、なおかつ届書にも不備がなければ受理されます。
しかし、本籍地に不受理申出がされていると、本籍地はもちろん、本籍地以外でも本籍地に電話等で確認できますから、申出人からの届出以外は受理されません。
申出人には不受理の通知がされる
不受理申出をしたことの効果として、申出人以外からの届出が受理されなかったときは、その旨が申出人に通知されます。
この通知は、住民異動届がされた現住所(戸籍の附票上の住所・住民票上の住所)を宛先としますが、転送不要で送られます。
したがって、不受理の通知を受けたければ、住民異動届をきちんと出して引っ越さなくてはならないので注意しましょう。役所に返送されると翌年中までは保管されます。
不受理申出後に本籍が変わる場合
不受理申出後に本籍が変わる場合、旧本籍地の市区町村から新本籍地の市区町村へ不受理申出書の原本が送られ、新本籍地の市区町村長に申し出たのと同じ扱いを受けます。
つまり、本籍が変わっても新たに不受理申出をする必要はありません。また、氏名や本籍の変更については、その変更履歴が保存されます。
不受理申出の有効期間
不受理申出には有効期間がなく、申出日から申出人が取り下げるまで効力は失われません(以前は6か月間でしたが廃止されました)。
ただし、本人が15歳未満で、不受理申出が法定代理人(または法定代理人となるべき人)からされた場合、15歳の誕生日の前日までが有効期間で、効力を持続させるには、15歳になった本人が改めて不受理を申し出なければなりません。
相手方の特定と不受理申出の失効
相手方を特定して不受理申出をすると、不受理の対象になった届出において、その相手方が不受理申出で特定した相手方と同じとき、届出の適法な受理によって不受理申出は失効します。
届出が適法に受理される条件は、不受理申出の申出人本人から届け出られるか、調停等の結果による届出です。申出人以外からの届出は受理されず、不受理申出の効力は保たれます。
ややこしいので、夫婦のAさんBさんを例に説明すると……
Aさんが、Bさんを相手方とした協議離婚届の不受理を申し出たとします。
AさんがBさんとの協議離婚届を出すと、不受理申出をしたAさん本人からの届出、なおかつ相手方はBさんなので、協議離婚届が受理されて不受理申出は失効します。
一方、BさんがAさんとの協議離婚届を出しても、Aさん本人からの届出ではないため受理されず、不受理申出の効力は保たれます。
不受理申出と対象の届出が入れ違ったら?
不受理申出をするのは、自分以外から勝手に届出される危険性が高く、受理されないように予防が必要と判断した場合でしょう。
しかし、不受理申出も対象の届出も、本籍地以外で申出・届出ができることを考えれば、自分以外から先に届出されたらどうしようと考えますよね。
不受理申出が、不受理にしたいと思っていた届出の後にされても、既に受理されてしまった届出を覆すことはできません。
しかし、不受理申出が届出の前にされていたのに、本来は不受理とすべき届出の受理で戸籍の記載がされてしまった場合は、市区町村が管轄の法務局長の許可を得て戸籍を訂正します(戸籍法第24条第2項)。
不受理申出が届出の前にされている限りは、不受理申出の効果が発揮されるということです。
不受理申出の取下げ
不受理申出は、申出人に限って取り下げることができ、不受理申出書と良く似た書式の取下書を提出します。不受理申出の取下書もダウンロード可能です。
北海道札幌市:不受理申出の取下げ
※別ウィンドウまたは別タブで開きます。
不受理申出書と似たような内容なので、書き方で混乱することはないでしょう。
不受理申出取下書の注意点
- どこの市区町村に提出するときでも宛先は本籍地の市区町村長
- 取下げの対象となる届出にチェックする
- 取下げ時の氏名、生年月日、住民票上の住所、本籍、筆頭者氏名(不受理申出時から変更があれば変更前の内容)
- 本人の署名
- 日中の昼間に連絡可能な連絡先
不受理申出の申出人が、市区町村の窓口に出頭して取り下げるのが原則で、本籍地以外の市区町村で取り下げても構いませんが、郵送による取下書の提出は、不受理申出と同様の制限を受けます。
不受理申出の取下げが受理されると、本籍地では不受理申出があったことを確認できるようにしていた措置を取りやめ、本人以外の届出でも受理できる状態に戻します。
また、本籍地以外の市区町村に取下書が提出されると、提出された市区町村で謄本が保管され、申出人の本籍地の市区町村に原本が送られる点は、不受理申出書と同じです。
まとめ:不受理申出
- 不受理申出は本人以外からの創設的届出を防止する役割
- 原則として本人が窓口に出頭して申し出る(郵送はかなり面倒)
- 不受理申出後も本人からの届出は受理される
- 有効期間はなく生涯有効(特定の条件下では失効)
- 不受理申出した本人は取り下げることも可能
不受理申出は、自分の意思と無関係な創設的届出について、将来への備えに活用できる制度です。
特に、第三者から戸籍謄本を不正に取得されると、知らない間に婚姻や養子縁組される危険性が高くなりますので、本人通知制度と不受理申出の併用をおすすめします。
また、調停で争うような関係性では、勝手に届出される可能性は常にありますし、いつでも自分で取り下げることができるため、不受理申出の利用価値はとても高いでしょう。